
様々な新着情報をお届けします
メルマガ
2025.07.31
SNSでもお役立ち情報を配信しています!いいね・フォローをお願いします。
夏バテに気を付けたいこの季節。乗り切るためにも栄養摂取が大切ですが、夏は食欲が低下しがちですよね。
今回は、暑さと摂食の関係について、ご紹介します。
実は1年を通じてみると、ヒトの体は季節によって基礎代謝量が違っており、夏は冬に比べて、基礎代謝量が低くなるのが一般的です。これは、恒温動物である我々ヒトが体温を保つために必要なエネルギーが気温の影響を受けることが要因の1つと考えられています。外気温が体温に近い夏は、冬に比べて体温保持に必要なエネルギー量が最小限で済みます。そのため、消費エネルギーが低下することにより、摂食行動が抑制されると考えられます。
夏は気温が高く、汗を大量にかくため、冷たいものがたくさん欲しくなります。冷たいものを食べると、即座に口の中や喉がスッキリし、涼しさを感じるため、暑さを和らげてくれるように思います。
しかし、このような行動が、夏の食欲不振の原因になることがあります。
食欲の恒常性調節系には消化管ホルモンも影響を及ぼしている2)ため、冷たい飲み物や食べ物の過剰摂取によって、体が冷えて胃や腸の働きが悪くなってしまうと、結果的に食欲が減退する原因となります。
自律神経は、体の様々な機能を自動的に調整する神経で、交感神経と副交感神経の2つの働きによって成り立っています。交感神経が活発になると、身体は戦闘モードに入り、食欲が抑えられます。一方、副交感神経が活発になると、身体はリラックスモードになり、食欲は亢進します。つまり、自律神経のバランスが崩れると、交感神経と副交感神経の働きがうまく調整できず、食欲が乱れます。
正反対の役割をもつこの2つの神経が、互いにバランスを取り合いながら働いているおかげで、私たちの健康は保たれていますが、夏は自律神経が乱れやすくなります。
その原因として、以下のようなものがあります。
● 脱水
体が脱水状態になると、水分がこれ以上減らないように細胞が血管とのつながりを閉じます。このような状態になると、交感神経が活発になり、食欲が抑えられます。また、血液が末端まで届きにくくなるため、疲れの原因にもなります。
● 屋内外の気温差
外と中の気温差が大きいと、自律神経が乱れやすくなります。特に外気温と室内の温度差が7度以上になると、自律神経が過剰に働き、「寒暖差疲労」が起こることがあります。
● 睡眠不足
睡眠不足は副交感神経の働きを低下させ、自律神経のバランスを崩します。熱帯夜で眠れなかったり、夜中に何度も目が覚めたりすると、眠りが浅くなり、血流が悪くなって脳の働きも低下します。自律神経のバランスが乱れることで血流が悪化し、全身に影響を与えます。
● 紫外線
人間は強い紫外線を浴びると、肌を守るためにメラニンを作る細胞が活発になり、肌が黒くなります。このとき、交感神経が働き、紫外線を浴び続けることでその状態が続き疲労がたまります。また、目は常に外界にさらされているため外部の刺激を受けやすく、目から入った紫外線の刺激は脳まで届き、交感神経を活性化させて自律神経のバランスを崩します。
暑い日が続きますが、体調には十分気を付けてください。元気に夏を乗り切りましょう!
【参考文献】
| 1) | 島岡 章ら. 基礎代謝の季節変動について. 日生気誌. 24(1): 3-8, 1987. |
| 2) | 上野 浩晶, 中里 雅光. 日本内科学会雑誌. 104(4): 717-722, 2015. |
オルトメディコでは健康食品のエビデンス取得も承っております。
試験の見積りや各検査項目の概要はこちらからご覧いただけます!
「食欲」を評価する試験も実施可能ですので
ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ!
 |
 |
|
 |
 |
|
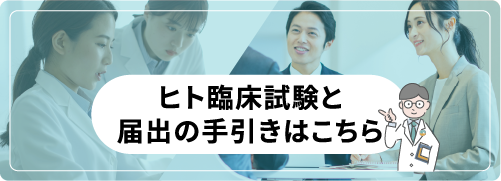 |
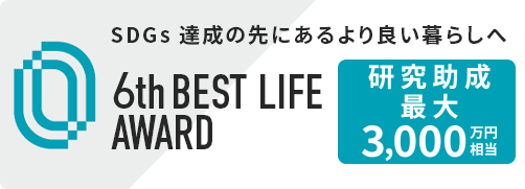 |
 |
 |
 |
 |
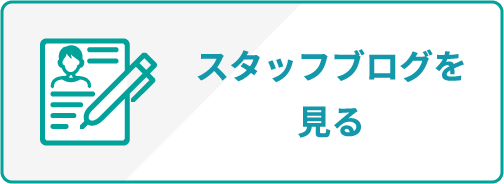 |
 |

ヒト臨床試験 (ヒト試験)
各種サポート業務等
各種お問い合わせは
お気軽にどうぞ
03-3812-0620 平日 | 9:00-17:00